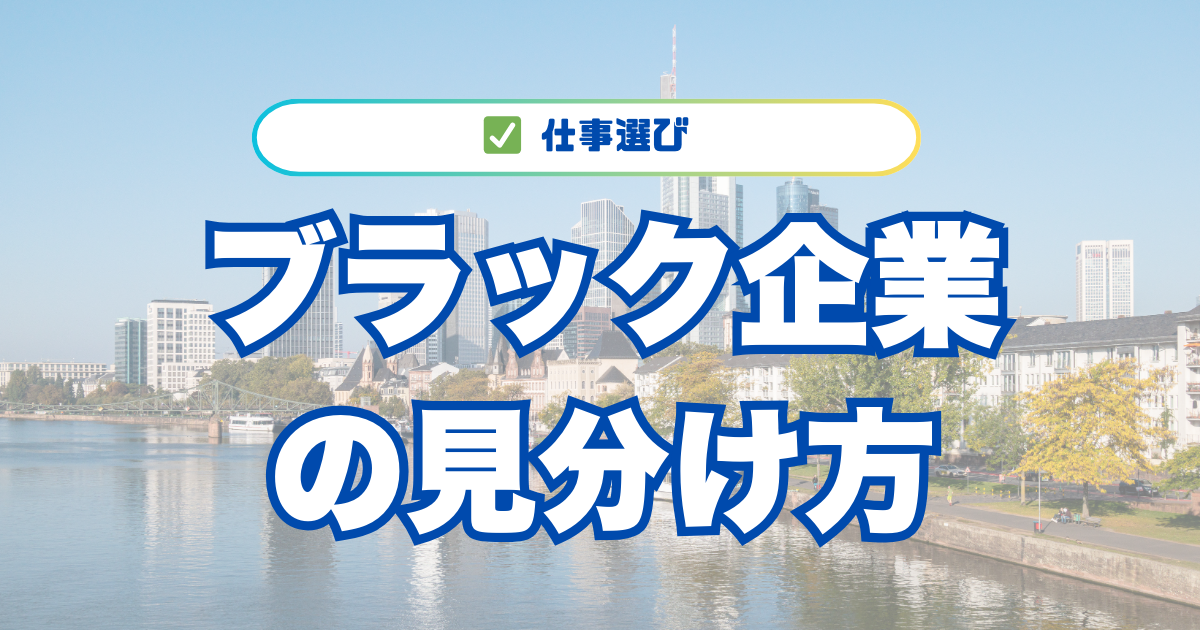転職活動を始めたいけど、ブラック企業だけは避けたい――
就職は実際に働いてみないとわからないことが多いですが、とはいえ、もし転職先がブラック企業だったらという心配はありますよね。
この記事では、求人票や企業の情報からブラック企業を見抜く具体的な方法を解説します。
見逃しがちなサインや、注意すべき言葉、ブラック企業を避けるための行動について、実例を交えてわかりやすく紹介します。
これから転職活動を始める方、職場に不安を感じている方にとって必見の内容です。
ブラック企業とは?|定義とよくある誤解

「ブラック企業」という言葉はよく耳にしますが、正確な定義を聞かれると答えに迷う人も多いかもしれません。
一言でいえば、法令違反や過剰な労働を強いるなど、従業員を使い捨てにする企業のことを指します。
厚生労働省においては、「ブラック企業」について定義していませんが、一般的な特徴として、① 労働者に対し極端な長時間労働やノルマを課す、② 賃金不払残業やパワーハラスメントが横行するなど企業全体のコンプライアンス意識が低い、③ このような状況下で労働者に対し過度の選別を行う、などと言われています。
代表的なブラック企業の特徴は以下のようなものです。
- 長時間労働・サービス残業が常態化している
- 上司や経営陣によるパワハラ・モラハラがある
- 労働条件が実態と異なる(求人情報に嘘がある)
- 離職率が極端に高い
- 有給休暇がほとんど取れない(申請すると嫌な顔をされる)
一方で、「厳しい職場=ブラック企業」とは限らないという点にも注意が必要です。
たとえば、成果主義が徹底された外資系企業では、勤務時間が長かったり競争が激しかったりすることがありますが、
労働環境や報酬制度が明確で適正であれば、それは「ブラック」とは言えません。
重要なのは、法令に違反しているかどうか、従業員の心身の健康や生活が守られているかどうかです。
ブラック企業の実態は巧妙に隠されていることが多く、
「うちはやりがい重視だから!」といった美辞麗句の裏に過酷な現実が潜んでいることもあります。
まずは、その“定義の曖昧さ”を理解し、冷静に情報を見極める目を養うことが大切です。
求人票に潜むブラック企業のサイン5選

ブラック企業かどうかは、求人票をよく読むことである程度見抜くことができます。
一見すると魅力的に見える文言の裏に、劣悪な労働環境が隠されていることも。
ここでは、求人票で分かる特徴5つをチェック
その1 頻繁に採用している
「この企業、先月も募集してたなぁ」と思ったことはないですか。あるいは、「いつでも募集中」とか記載されていたら、この企業は危険信号です。
離職率が高いと、人が不足している状態になりやすいので、しょっちゅう募集することになります。人が定着しないというのは、何か原因があるのでしょう。それこそ、長時間労働が常態化していたり、ハラスメントが横行していたり、組織に何かしらの問題があるという可能性が高いと言えます。
人不足→従業員が疲弊→退職者・休職者が続出→人不足、という負のスパイラルにはまってしまっていると、よほどの改革者が現れたとしても、脱出するのは相当の時間がかかるでしょう。
業界や雇用体系によっても異なりますが、正社員の場合、離職率は20%を超えると注意が必要です。
つまり、100人規模の企業で、年間で20名以上の募集をしているようであれば、警戒した方がいいでしょう。
その2 採用基準が低すぎる
「業界未経験可」とか「学歴不問」などは結構見かけますが、「書類選考なし」「誰でもできるお仕事です」っていうのは、ちょっと怪しくなってきます。
採用が全然うまくいかないから、誰でもいいから欲しいというのが透けて見えます。少なくとも人気のある企業だと、書類選考もせずに採用するってことはないはずですよね。
かつて僕が働いた職場でも、人が採用できなくなると、どうにか人を集めるために、どんどん採用基準を低くしていきました。履歴書不要の手ぶら面接とか、WEB面接とか、とにかく簡単に応募しやすくしたし、本当は採用したくないけど人が足りないよりましかもしれないという「チャレンジ採用」というのを増やしました。
こういう採用の仕方をすると、従業員の質が低下し、コンプライアンス違反するような従業員が増えて、企業にとっていいことはなかったというのが実感です。
日本は全国的に労働者不足になってきて、採用競争が激化しているので、基準を下げたからブラック企業だということでもないかもしれません。ただ中途採用というのは即戦力がほしいので、未経験者でもいいというのはよほど人気がないのでしょう。誰でもできる仕事というのはいずれAIでもできてしまう可能性もありますし、避けたほうがいい仕事の可能性が高いと言えるでしょう。
その3 報酬が異様に高い
優良な企業であればこそ、給料が高い傾向にあるのは確かです。優秀な人材がそろって、安定しているので、効率よく稼ぐことに成功しているからでしょう。
ですが、「この企業って結構最近できたんじゃないの?」とか「この業界って、そんなに儲かるんだっけ?」と思うような企業が相場よりも高い給料で募集していると、ちょっと疑った方がいいでしょう。
高い理由として、業績給や固定残業代が含まれた金額を提示しているケースが多いんじゃないでしょうか。例えば、給料50万円と募集広告に記載されていた場合、実態は営業などで一定のノルマを達成した場合であったり、みなし残業時間が設定されているというケースです。
広告の中に小さく但し書きがされているようであれば、まだ救いがあると思いますが、何も条件などが記載されていないのに、異様に高い給料設定はやはり怪しむべきでしょう。
そのような企業は、高いノルマが設定されていたり、みなし残業時間よりもはるかに長い残業時間を強いられたうえに、みなし残業時間を超えた残業代を無視されるようなこともあり得るでしょう。
その4 あいまいな言葉が多い
皆さんは、評価面談などの自己アピールする必要がある場面で、客観的なデータでアピールできない場合、どうやってアピールしますか?
おそらく、一生懸命やりましたとか、元気よく対応しましたが、仲間と協力して頑張りましたとか、雰囲気でアピールするしかないですよね。
企業も同じです。企業の広告で「未来」「やりがい」「挑戦」「アットホーム」「笑顔」「夢に向かって」みたいなワードはよく目にします。もしそのような精神論だけしか提示していなければ、ほかに示せるアピールポイントがないのかもしれません。
転職者からすれば、業務内容や福利厚生制度、報酬体系、平均残業時間、年間休日日数などの具体的な内容を知りたいわけです。なのに、仕事のやりがいや熱意などを誇張し、具体的な内容を出さないのは、不都合な真実を隠している可能性があります。
その5 社名がコロコロ変わる
ブランド価値を築いた企業だったら、社名を変えたくはないはずですよね。合併したり、経営陣を刷新して新しくスタートしようとしたり、大きな方針転換をする場合など、変える必要がある場合ならともなく、なんのために社名を変えたのか分からないし、数年の内に2回も3回も変更している企業は要注意です。
それこそ、悪い噂が広がって、ネット上でもブラック企業として検索で引っかかるようになったとか、違法行為で摘発されたとか、何かしら以前の社名を隠そうとして変えている可能性があります。
オフィシャルホームページで、その企業の歴史や沿革を確認し、不自然な点がある場合は近寄らないほうがいいでしょう。
口コミサイトやSNSなどで会社の実態をチェックする方法

求人票だけでは見えてこない会社の内情を知るには、口コミサイトやSNSなどの「他人からの情報」の活用が効果的です。
実際に働いていた人の声は、職場のリアルな実態を教えてくれる貴重な情報源です。
口コミサイト
主な口コミサイトと活用ポイント
- OpenWork(旧Vorkers):企業ごとの評価が細かく、待遇や風土についての詳細なレビューが多い
- 転職会議:在籍経験者・元社員の口コミが豊富で、リアルな労働環境がわかる
- ライトハウス(旧カイシャの評判):職場の雰囲気や制度に関する定量的なデータも確認できる
これらの口コミはすべてを鵜呑みにするのではなく、「共通して指摘されている内容」に注目しましょう。
たとえば「残業が多い」「上司のパワハラがひどい」など、同じ内容が複数のレビューに見られる場合は信憑性が高いといえます。
SNS
TwitterやX(旧Twitter)・Instagram・noteなどのSNSでも、「#会社名」「#ブラック企業」などで検索すると、在籍経験者や退職者の投稿を見つけられることがあります。
注意点として、SNSや口コミはあくまで主観的な意見です。
人と人との関係と同じで、人と企業との関係にも相性や反りが合う・合わないがあるので、情報をすべて丸のみするのは危険です。実名ではないこともあって、不正確な情報も混じっていることを理解して、全体的に目を通すくらいでいいと思います。
悪い情報がたくさん書かれているようであれば、それなりの理由があるので、参考にはなるでしょう。
ブラック企業リスト
正式名称は「労働基準関係法令違反に係る公表事案」といいますが、厚生労働省が公表しているいわゆるブラック企業リストなるものがあります。
厚生労働省のホームページ上で、企業名、所在地、法令違反の事案概要などが掲載されているので、誰でも確認することが可能です。
公式にブラックな会社として認定されている企業になるので、就職しようとしている企業が掲載されていないかぐらいは確認しておいた方がいいでしょう。
就職四季報のチェック
就職四季報は、東洋経済新聞社が発行する、就活生に役立つ企業情報が掲載されたデータブックです。企業の業績や採用実績、働き方などの情報が掲載されており、就活序盤の志望企業探しや選考試験対策に活用できます。
記者が一社一社を独自に取材し、会社パンフレットやホームページに掲載されている宣伝のような情報ではなく、データに裏付けされた中立的・客観的な情報を掲載しています。会社から掲載料はもらっていませんので、信用できるデータだと思います
「3年後離職率」「残業時間数」「有給取得日数」など、他の就職情報誌では見ることができない重要な情報が載っているので、求人票では確認できない情報も確認することができます。
企業名で検索する
ヤバいキーワードと企業名をセットで検索してみると、検討していた企業がヒットするなんてこともあります。
ヤバいキーワードというのは、例えば次のようなものです。
「違法」「違反」「不正」「不祥事」「起訴」「送検」「逮捕」「訴訟」「起訴」「裁判」「処分」⋯⋯などなど
もしヒットした場合は、必ずヒットした記事の内容を確認しておきましょう。
過去に法令違反を行って、処分を受けている企業は要注意です。不正を行う企業はそれが文化になっている可能性もあります。
処分を受けて是正する企業もありますが、不正の実行者は役員や管理職が多いことから、一度不正をした企業は繰り返す傾向にあるようです。特に大企業や歴史のある企業では感覚が麻痺しやすく、一部の人が企業文化を変えようと思ってもなかなか変わりにくいのが現実ですね。
面接で見抜く!ブラック企業かどうかを判断する質問

求人票や口コミだけではわからないことも、面接の場で直接質問することで見えてくることがあります。
ここでは、ブラック企業かどうかを判断するために有効な「逆質問」の例をご紹介します。
おすすめの質問例:
- 「社員の平均的な残業時間はどれくらいですか?」
残業の有無だけでなく、平均時間を聞くことで実態に近い情報が得られます。 - 「有給休暇の取得率や取得しやすさについて教えてください」
取得率や制度だけでなく、「実際に取れているか」も確認できるポイントです。 - 「前任者が退職された理由は?」
採用背景を尋ねることで、離職率や人間関係の問題を探る手がかりになります。 - 「社員の平均勤続年数はどれくらいですか?」
長く働ける環境かどうか、社内の定着率が見えてきます。
面接では、企業側もあなたを見ていますが、こちらも企業を見極めるチャンスです。
質問への回答が曖昧だったり、ごまかされたりする場合は、注意が必要です。
逆質問を通じて、企業が本当に「働きやすい環境」を整えているのか、あなた自身の目と耳で確かめる姿勢が大切です。
それでも不安なら?転職エージェントを味方につけよう

「求人票もチェックした」「口コミも調べた」「面接もした」――それでもまだ不安が残る。
そんなときに頼れる存在が、転職エージェントです。
転職活動をする時、転職サイトや転職エージェントを活用する人が多いと思いますが、転職エージェントを使った方がブラック企業に合う確率が低いです。
というのも、転職エージェントの場合、採用したら企業が紹介料を払う仕組みになっているからです。紹介料は安くありません。高いコストを払ってすぐに辞められると非常にもったいないですよね。なので、転職エージェントを使っている企業は、人材を大事にする意識が高く、ホワイト企業である率が高いのです。
採用活動にお金をかけるのは、人材に投資する気持ちがあるからですよね。その気持があって、ちゃんと利益が出ているから高いコストをかけて、いい人材を採用しようと思うわけです。
逆に、人材に高い投資をしようとしない企業はそもそも高コストになる転職エージェントを使っていないケースが多くなります。
構造的な問題からも、転職エージェントの活用はおすすめできます。
とくに、ブラック企業を避けたい人にとっては、次のような点が大きなメリットです。
- 紹介先企業の労働環境について事前に教えてくれる
エージェントは企業の採用担当者とやり取りしているため、現場のリアルな情報を知っていることが多いです。 - ブラック企業を排除してくれる傾向がある
信頼を失うとビジネスに支障が出るため、評判の悪い企業とは取引を控えるエージェントが多い。 - 希望条件に合った企業を第三者目線で探してくれる
自分で探すと見落としがちなポイントも、プロの視点でカバーしてくれます。
転職活動をひとりで進めるのは不安が多いもの。
信頼できるエージェントを活用することで、ブラック企業に入社するリスクを大幅に減らすことができます。
登録も相談も無料なので、まずは話を聞いてみるだけでも十分に価値があります。
ホワイト企業の7つの特徴

ブラック企業を避けるためにも、ホワイト企業の特徴を知っておいた方がいいでしょう。ちなみに、ブラック企業の真逆の特徴になります。
ホワイト企業の具体的な特徴は主に次のような点です。
| ホワイト | ブラック | |
|---|---|---|
| 離職率 | 低い。 職場環境がいいことを表しています。 | 高い。 |
| 残業時間 | 少ない。 ワークライフバランスがとりやすく、従業員の心身の健康やモチベーションの維持につながります。 | 多い。 |
| 福利厚生 | 充実している。 雇用保険や健康保険など社会保険料を企業が負担する法定福利厚生だけでなく、各種休暇制度や住宅手当、勤務制度など、企業独自の福利厚生が充実していると、働きやすい環境づくりに積極的だといえます。 | 不十分。 |
| コンプライアンス | 遵守を徹底している。 企業全体としてコンプライアンスに関する意識が高く、またそのための教育制度も整っています。コンプライアンスを徹底することで、企業や従業員が守られ、企業の健全な発展につながります。 | 遵守意識が低い。 |
| 評価制度 | 明確。 自分の働きがどのように評価され、昇給や昇格に反映されるのかが明確になっていれば、従業員は自身のキャリアプランを立てやすくなり、目標意識を持って意欲的に働けます。 | あいまい。 |
| 人材育成 | 長期視点で育成。 従業員が長期的に勤務することを前提に人材育成・教育制度が構築されているため、能力やスキルを向上させる仕組みが整っています。 | 使い捨て。 |
| 給料支払 | 適切に支払われている。 適切な額の給料を遅滞なく支払う能力があるということは企業が安定し、また従業員を大切にしていることを意味します。 | 未払い・誤払いが多発 |
これらの特徴により、従業員の働きやすさと企業の安定的な成長が両立されています。
まとめ|ブラック企業を見抜く目を持って、自分の未来を守ろう
ブラック企業に入ってしまうと、心身の健康を損ない、人生の大切な時間を浪費してしまう可能性があります。
しかし、事前にしっかりと情報収集し、見極める目を養えば、そのリスクは大きく下げられます。
本記事でご紹介したようにーー
- 求人票に潜む“危険な言葉”を読み解く
- 口コミサイトやSNSで実態を確認する
- 面接時の質問で企業の本音を探る
- 転職エージェントのサポートを活用する
といった方法を組み合わせることで、ブラック企業を避ける力が自然と身についていきます。
そして何より大切なのは、「違和感」を見逃さないことです。
「おかしいな」「なんとなくイヤな感じがするな」と思った直感は、案外当たっているもの。
自分の人生を守れるのは、最終的には自分だけです。
無理に妥協せず、納得できる職場を見つけるために、冷静かつ慎重に選択していきましょう。