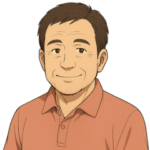 初心者さん
初心者さん投資はしてるけど、資産のうち、どれくらいを投資にまわすのがいいのかな。FIRE達成した人って、どんな割合なんだろう。
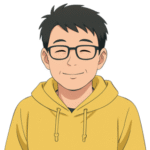
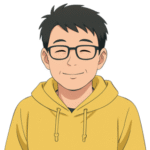
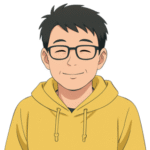
確かに、FIRE(経済的自立・早期リタイア)を目指すうえで、多くの人が悩むのが「資産のうち、どれくらいを投資にまわすべきか?」という問題ですね。
投資で資産を増やすことはFIRE実現に欠かせませんが、すべてを投資に回せば安心して生活するための資金が足りなくなるリスクも出てきます。
今回の記事では、生活防衛資金の考え方や、リスク資産と安全資産の役割、ライフプランに応じた投資割合の決め方について、わかりやすく解説していきます。
「増やす」と「守る」のバランスをとりながら、FIRE実現に向けた最適な資産配分を考えていきましょう。
なぜ投資割合がFIRE成功のカギになるのか?


FIREにおいては、働かずに生活する期間を乗り切るだけの資産を確保する必要があります。
そのため、資産を現金で寝かせておくだけでは不十分。インフレや支出に対応しながら資産を維持・成長させるために、投資という種まきにある程度の割合をまわすことが求められます。
投資なしではFIREは成立しない
FIREを目指す上では、収入源が限られる中で「資産が資産を生む」構造を作る必要があります。
その中心になるのが、インデックス投資や高配当株、債券などの資産運用です。
一定以上の利回りがなければ、FIRE後に資産が目減りし、生活が破綻するリスクも。
とはいえ“全額投資”は危険
投資にまわす割合を増やせば増やすほどリターンは大きくなりますが、その分暴落時のダメージも大きくなるというリスクがあります。
FIRE直後にリーマンショック級の下落が来れば、取り崩し戦略が破綻することもありえます。
投資割合=FIRE生活の安定性に直結
だからこそ、「どれだけ投資に回すか」はFIREの実現だけでなく、その後の安定した生活を維持できるかどうかにも関わってくる重要な要素です。
次のパートでは、現金で持っておくべき生活防衛資金について詳しく見ていきましょう。
生活防衛資金とは?どこまで現金で持っておくべきか


FIREを目指すうえで、まず優先すべきなのが「生活防衛資金の確保」です。
これは、万が一収入がなくなったり、急な支出が発生したときに備える“現金による安全資産”のことを指します。
生活防衛資金は「安心の土台」
株式などのリスク資産は、長期で見れば成長が期待できますが、短期的な暴落や元本割れのリスクがあります。
生活防衛資金がない状態でFIREをすると、相場が不調なときでも資産を取り崩すしかなくなり、結果的にFIRE生活が不安定になります。
どれくらいの金額を持っておくべきか?
必要な生活防衛資金は、収入や支出によっても変わりますが、目安は下記のとおりです。
- サイドFIREや副業収入がある場合:生活費の3〜6ヶ月分
- 完全リタイアの場合:生活費の1〜2年分が目安
- 持病・家族・高齢の親などの要因がある人:さらに多めに確保しておくと安心
この資金は銀行預金や普通預金口座など、すぐ引き出せる形で保有するのが基本です。
生活防衛資金を算出するためには、生活費を把握する必要があります。
生活費に関しては下記の記事も参考にしてください。
生活防衛資金を確保してからが「投資のスタート」
リスク資産にお金をまわすのは、生活防衛資金を確保してからが鉄則です。
「投資は早く始めたほうがいい」とはよく言われますが、精神的な安定がない状態で投資をしても、暴落時に耐えられず損切りしてしまう可能性が高くなります。
次のパートでは、投資にまわす資産をどう振り分けるかのカギとなる、「リスク資産と安全資産の違いと役割」について解説していきます。
リスク資産と安全資産の違いと役割を理解しよう


資産運用を考える上で欠かせないのが、資産の性質を「リスク資産」と「安全資産」に分けて考えるという視点です。
この分類を理解していないと、資産配分を決める際にバランスを崩し、リスクを取りすぎたり、リターンを逃したりすることにつながります。
リスク資産とは?
- 値動きがある=価格が上下する可能性がある資産
- 長期的にはリターンを期待できるが、短期的には損失もありうる
- 例:株式・投資信託・REIT・仮想通貨・外貨など
FIREを目指すなら、このリスク資産で資産を増やすことが基本戦略になります。
安全資産とは?
- 原則として元本が保証されている、または値動きが非常に小さい資産
- 例:現金・預金・国債・一部の個人向け社債など
安全資産は、暴落時の“クッション”となり、精神的な安定を保つ役割を果たします。
どちらが良い悪いではなく、役割の違い
リスク資産=攻め
安全資産=守り
FIREにおいては、この両方をどう組み合わせるかが非常に重要です。
すべてをリスク資産にすればリターンは大きくなりますが、不測の事態に弱くなります。
逆に安全資産ばかりでは、資産が増えずFIREの達成が遠のきます。
次のパートでは、実際にFIREを目指すなら、どれくらいの割合を投資にまわすべきか?について考えていきましょう。
FIREを目指すなら投資にまわすべき資産の割合は?
では実際に、FIREを目指す場合、手元の資産のうちどれくらいを投資にまわせばよいのでしょうか?
答えは一つではありませんが、いくつかの基準や考え方を知っておくことで、あなた自身に合った配分が見えてきます。
基本の目安は「生活防衛資金を除いた分を投資へ」
まず前提として、生活費の6ヶ月〜2年分は現金で確保しておき、それ以外の資産を投資にまわすのが基本です。
この考え方をベースに、以下のようなパターンが考えられます。
■ ケース別の投資割合の目安
- 独身・若年層・収入安定:リスク許容度が高いため投資割合80〜90%
- 家族あり・教育費負担大:投資割合は50〜70%程度が現実的
- 完全FIREを目指す場合:投資割合70〜90%が必要になることが多い
- サイドFIREや副業あり:現金比率をやや抑えて80%前後投資も可能
このように、収入状況・家族構成・ライフプランに応じて投資割合は調整すべきです。
「リスク資産の取り崩し」が現実になるFIREでは重要
FIRE後は、投資資産を取り崩して生活費をまかなうことになります。
だからこそ、どのくらい投資にまわし、どのくらい現金・債券などの“守り”の資産を残しておくかは、FIREの成功に直結します。
4%ルールとの関係
FIRE界隈で有名な「4%ルール」では、年4%の取り崩しで30年持つ資産運用が前提です。
この運用を実現するには、株式7割+債券3割のような高いリスク資産比率が求められるケースも多く、やはり投資にまわす割合は大きくなりがちです。
次のパートでは、ライフプランによってどのように運用割合を調整すべきかを具体的に解説していきます。
年齢・家族構成・ライフプラン別の運用戦略
投資にまわす資産の割合は、年齢・家族構成・ライフプランによって柔軟に調整すべきです。
10年以上使う予定がない資産は投資にまわしてもいいですが、2〜3年後に必要になる資産を投資にまわすと、必要になるタイミングで暴落していると、大きな損失にもなりかねません。
そのため、ライフプランを可視化して、どこまでリスクを背負うかを考えて、調整する必要があるのです。
ライフプランとは?
人生の節目や目標(結婚、子育て、住宅購入、退職など)に合わせて、将来の収入・支出・貯蓄・資産運用などを見通しながら立てる「人生のお金の設計図」です。FIREを目指すなら、いつまでにいくら必要かを明確にするためにも欠かせない視点です。
<サンプル:ライフプラン表> ※クリックすると開きます
| 年齢 | 年収 (手取り) | 家族構成 | 主なイベント | 貯蓄額 | 投資資産 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35歳 | 500万円 | 妻・子3歳 | 教育資金積立開始 | 300万円 | 500万円 | iDeCo・新NISA活用開始 |
| 40歳 | 520万円 | 妻・子8歳 | 子ども小学校入学 | 800万円 | 1,500万円 | 投資資産の成長が加速 |
| 45歳 | 550万円 | 妻・子13歳 | 住宅ローン完済予定 | 1,200万円 | 3,000万円 | FIREに向け生活費見直し実行 |
| 50歳 | 0円(FIRE達成) | 妻・子18歳 | 完全リタイア | 1,000万円(現金) | 6,500万円 | 配当+定率取り崩し開始 |
| 55歳 | 0円 | 妻・子大学生 | 子ども大学卒業予定 | 700万円 | 5,000万円 | 生活費は資産から取り崩し中 |
| 60歳 | 0円 | 妻 | 年金受給まであと5年 | 500万円 | 3,500万円 | セーフティ資金や国債の割合増 |
| 65歳 | 年金開始 | 妻 | 年金(夫婦で年200万円想定) | 300万円 | 2,000万円 | 年金+一部取り崩しで生活維持 |
ここでは、よくあるパターンごとに、考えるべき運用戦略のヒントを紹介します。
① 20〜30代・独身・FIRE初期層
- リスク許容度が高く、資産も少ない段階
- 生活防衛資金以外は80〜90%を投資に
- 積極的に成長資産(株式・インデックスファンド)で運用してOK
② 30〜40代・既婚・子どもあり
- 教育費・住宅費など支出が増えやすい
- 生活防衛資金を厚めに(12ヶ月以上)
- 投資割合は50〜70%が目安
- 安全資産とのバランスをとって運用を安定化
③ 50代以降・FIRE直前 or 完全FIREを視野
- これからリタイアを控える段階
- 暴落耐性を高めるため、安全資産を増やす
- 投資割合は50〜70%、債券や現金比率を高めて調整
- ポートフォリオのリバランスが重要
④ サイドFIRE・副業あり・柔軟な働き方
- 収入源が複数あるためリスク分散されている
- 生活防衛資金は少なめでもOK(3〜6ヶ月)
- 投資割合80%前後でも運用しやすい
このように、自分のライフステージとリスク許容度に応じて、資産配分を変化させるのがFIRE戦略の基本です。
次のパートでは、この資産配分は“固定”ではなく、ライフイベントや相場状況に応じて見直すべきというリバランスの重要性についてお伝えします。
投資割合は“変えていい”|状況に応じてリバランスを


FIREを目指す資産配分は、一度決めたら終わりではなく、状況に応じて見直す=リバランスが重要です。
人生は常に変化します。家族構成、収入、健康状態、相場環境などによって、最適な資産配分は変わって当然です。
リバランスのタイミングは?
- 1年に1回程度が基本(年末などに見直す習慣を)
- 相場が大きく動いたとき(例:株価が急落して投資比率が下がったとき)
- ライフイベント発生時(結婚・出産・転職・引越し・退職など)
たとえば、株式市場が好調で投資資産が膨らんだときは、一部を現金に戻して安全資産を増やすといった調整も効果的です。
FIRE後も見直しは必要
FIREを達成したあとも、資産を守りながら取り崩していくには、定期的な配分調整=リバランスが不可欠です。
特に取り崩し初期に暴落があるとダメージが大きいため、安全資産比率を高める「バッファ戦略」が有効です。
自分で決められないときは?
「どのくらいの割合がいいのかわからない」「調整が面倒」という人はーー
- ロボアドバイザーを活用する
- バランス型ファンド(例:全世界株式+債券)を選ぶ
- プロが設計したポートフォリオ例を参考にする
といった方法もありますが、当然少なからず手数料が必要となります。
大切なのは、今の自分に合った形で投資割合を保つこと。完璧を求める必要はありません。
それでも悩む場合は、まずはなくなってもいいくらいの少額から始めて、少しずつ増やしていけばいいです。
次のパートでは、この記事全体のまとめとして、安心とリターンを両立させる資産配分の考え方を振り返ります。
まとめ|安心とリターンを両立させる資産配分の思考法
FIREを目指す上で、「投資にまわす割合」は非常に重要なテーマです。
資産配分を誤れば、目標に届かないばかりか、FIRE後の生活が不安定になるリスクもあります。
今回ご紹介したポイントを振り返ってみましょう。
- まずは生活防衛資金(6ヶ月〜2年分)を現金で確保する
- 残りの資産をリスク資産(株式・投資信託など)で運用
- 年齢・家族構成・収入状況に応じて投資割合を調整する
- 資産配分は一度決めたら終わりではなく、定期的にリバランス
FIREを目指す人の多くは、「とにかく投資しなければ」と焦ってしまいがちですが、安心して継続できる仕組みを作ることが成功のカギです。
“増やす”と“守る”をバランスよく考える。
それが、FIREという長期的なゴールに向けた、最も堅実で持続可能な道となるでしょう。
あなたの今の資産配分、見直してみませんか?

