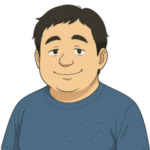 初心者さん
初心者さん投資信託とETFって、何が違うの?
新NISAではどちらを選べばいいのか分かんない
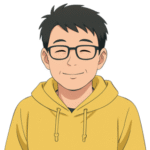
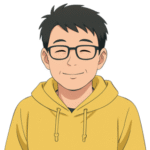
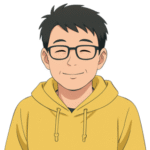
投資を始めようとしたとき、必ずぶつかるこの疑問ですね。
どちらも長期投資に向いた商品だけど、仕組みやコスト、購入方法に意外な違いがあるので、詳しく説明していきますね。
今回の記事では、投資信託とETF(上場投資信託)の違いをわかりやすく解説しながら、それぞれのメリット・デメリット・向いている人まで徹底比較。
新NISAでの選び方のヒントも紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
そもそもETFと投資信託とは?|基本の仕組みをわかりやすく解説


「投資信託もETFも、どちらもファンドでしょ?」
たしかにどちらも複数の銘柄(株や債券)をまとめて運用する金融商品という点では共通しています。
しかし、その運用方法・購入方法・取引スタイルには大きな違いがあります。
投資信託(ファンド)とは?
投資信託は、私たち投資家が出したお金を専門の運用会社が集めて、プロが代わりに運用してくれる仕組みの商品です。
- ファンドにお金を預ける
- 運用会社がそのお金で株や債券に分散投資
- 得られた利益は「基準価額」の上昇として反映される
という仕組みです。
1日1回決まる「基準価額」で売買されるため、時間を気にせず買えるのが特徴です。
ETF(上場投資信託)とは?
ETFは「上場投資信託(Exchange Traded Fund)」の略で、投資信託の一種が証券取引所に上場されているものです。
株と同じように、証券市場でリアルタイムに売買されるため、
- 日中に価格が変動する
- 指値・成行注文ができる
- 取引時間内ならいつでも売買できる
という株取引のような自由さがあるのが特徴です。
共通点と違いを一言でまとめると?
ざっくり言えば、
- 投資信託=「プロ任せで手間なし・自動積立に強い」
- ETF=「自分で売買タイミングをコントロールできる・コストが安い傾向」
という違いがあります。
次のパートでは、この2つの違いを5つの視点からさらに詳しく比較していきます。
投資信託とETFの違いを比較|5つの視点で徹底チェック


投資信託とETFは、どちらも「分散投資ができるファンド」という共通点がありますが、仕組みや取引スタイルには明確な違いがあります。
ここでは、初心者が特に気になる5つの観点から、両者を比較してみます。
比較①:売買の方法とタイミング
- 投資信託:1日1回の基準価額で売買(リアルタイムで価格は動かない)
- ETF:株と同じように証券取引所でリアルタイムに売買が可能
➡️ 初心者には「価格がわかりやすい投資信託」が安心。
一方、取引のタイミングを自分で判断したい人はETF向きです。
比較②:購入方法
- 投資信託:1円単位で購入可能。クレジットカード積立も対応(楽天・SBIなど)
- ETF:証券口座で1口単位で購入(価格はその時々で変動)
➡️ 自動でコツコツ積み立てたいなら投資信託のほうが柔軟です。
比較③:コスト(信託報酬・取引手数料)
- 投資信託:ノーロード(購入手数料無料)が多いが、信託報酬はETFよりやや高め
- ETF:信託報酬がかなり低め。売買手数料がかかるケースもあり
➡️ 長期的なコストパフォーマンスを重視するならETFが有利な場合もあります。
比較④:分配金の扱い
- 投資信託:再投資型が主流。自動で再投資されるため手間いらず
- ETF:分配金は現金で受け取り。自分で再投資する必要あり
➡️ 放っておいても資産が増える仕組みがいい人には投資信託がおすすめ。
比較⑤:取扱本数と選びやすさ
- 投資信託:数千本から選べる。人気ランキングや評価が充実
- ETF:国内外合わせて数百本。インデックス連動型が主流
➡️ 初心者が「選びやすい」「比較しやすい」のは投資信託です。
比較まとめ表
| 比較項目 | 投資信託 | ETF |
|---|---|---|
| 売買方法 | 基準価額(1日1回) | 株式と同様、リアルタイム取引 |
| 購入単位 | 1円からOK、自動積立◎ | 1口単位、証券口座が必要 |
| 信託報酬 | やや高め | 低め |
| 分配金の扱い | 自動再投資が主流 | 現金で受取、自分で再投資 |
| 選びやすさ | 本数豊富、初心者向け | 選択肢少なめ、上級者向けも |
次のパートでは、この違いの中でも「コスト」に注目し、ETFと投資信託それぞれの費用構造について詳しく見ていきます。
コストで見る投資信託とETF|信託報酬・手数料の違い
投資を長く続けるうえで、意外と見落とされがちなのが「コストの差」です。
どちらも“長期保有向け”の商品ですが、毎年かかる費用(信託報酬)や取引時のコストには違いがあります。
信託報酬の違い|ETFの方が基本的に安い
信託報酬とは、ファンドを運用してもらうためにかかる年率ベースの運用手数料です。保有している間、ずっと引かれ続けるため、少しの差でも長期では大きな差になります。
| 商品タイプ | 信託報酬の目安(年率) |
|---|---|
| インデックス型投資信託(例:eMAXIS Slim) | 0.1〜0.2%程度 |
| ETF(例:MAXIS ETF、VOOなど) | 0.05〜0.15%程度 |
➡️ 一般的にはETFの方が信託報酬が低く、コスト効率が良いとされています。
売買手数料の違い|ETFには注意が必要
投資信託は「ノーロード(買付手数料無料)」の商品が多く、楽天証券やSBI証券などでは売買手数料ゼロで始められるものがほとんどです。
一方、ETFは株式と同様に売買手数料がかかる場合があります。
- 楽天証券・SBI証券などでは、国内ETFの取引手数料は基本的に無料
- 米国ETFは約定ごとに手数料(例:0.495%など)がかかる場合も
➡️ 少額で積み立てたい人は、投資信託の方がコスト面で優位です。
隠れコストにも注目しよう
ETFには「スプレッド(売買価格の差)」というコストも発生します。
これは、買値と売値の差額=実質的な手数料のようなものです。
流動性が低いETFほどスプレッドが広がりやすいため、頻繁な売買には向いていません。
長期投資なら「トータルコスト」で考える
- 信託報酬は毎年
- 売買手数料は取引ごと
- スプレッドはタイミングごと
このようにコストの種類が異なるため、「自分がどのくらいの頻度・金額で取引するか」を考慮したうえで、最適な商品を選ぶことが重要です。
次のパートでは、投資信託とETFの「買い方・使い方」の違いについて具体的に解説していきます。
買い方・取引方法の違い|初心者でも簡単なのは?
投資信託とETFの違いは、「何に投資しているか」よりも「どうやって買うか」に大きく表れます。
ここでは、両者の購入方法・取引のしやすさ・管理の手間を比較しながら、初心者にとって使いやすいのはどちらかを解説します。
投資信託は「選んで、積み立てるだけ」
投資信託は、証券会社のウェブサイトやアプリでファンドを選び、金額を指定するだけで購入できます。
- クレジットカード積立対応(楽天カード・三井住友カードなど)
- つみたて設定をすれば、あとは自動で買付される
- 1円単位から買える
放っておいても積み立ててくれる安心感があり、初心者や忙しい人にぴったりです。
ETFは「株式のように自分で取引」
ETFは、証券取引所に上場しているため、株と同じ感覚で売買します。
- 証券口座内で「銘柄コード」や「ティッカー」で検索
- 成行・指値注文など、注文方法を選択
- 価格が動くので、タイミングによって損益が変わる
リアルタイム取引ができる反面、「いつ買うか」「いくらで買うか」の判断が必要になるため、やや上級者向けです。
初心者には“ほったらかし”ができる投資信託が人気
自動積立・再投資・低ストレスといった点で、はじめて資産運用を始める方には投資信託のほうが扱いやすい傾向があります。
ただし、ETFにも「月1回だけ買い増す」「ボーナス月にまとめ買いする」など、自分で取引を楽しみたい人に向いているスタイルがあります。
次のパートでは、新NISA制度において、ETFと投資信託のどちらが向いているのかを具体的に解説していきます。
新NISAではどっちを選ぶべき?|つみたて投資枠・成長投資枠との相性


2024年からスタートした新NISA制度では、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つが用意されています。
それぞれの枠で投資信託とETFのどちらが適しているかを見ていきましょう。
つみたて投資枠は「投資信託」が対象
つみたて投資枠は、金融庁が定めた基準を満たす一定の投資信託のみが対象です。
ETFはこの枠では使えません。
対象となるファンドの特徴ーー
- 手数料が低い
- 長期・積立・分散投資に適している
- 販売会社が変更できない仕組み
➡️ 自動積立・ほったらかし運用をしたい人には、つみたて投資枠×投資信託の組み合わせが最適です。
成長投資枠では「ETF」も利用できる
一方、成長投資枠では、ETFも個別株と同様に購入可能です。
利用できる商品ーー
- 国内外のETF(例:2558、2631、VT、VOOなど)
- インデックス型・テーマ型など多様なETF
➡️ 低コストで効率的に指数に連動する資産形成をしたい人は、ETFを活用する価値ありです。
両方使って「投信+ETF」の戦略も◎
新NISAの魅力は、つみたて投資枠と成長投資枠を同時に活用できる点にあります。
たとえばーー
- つみたて投資枠で:毎月の自動積立(投資信託)
- 成長投資枠で:年に数回のスポット買付(ETF)
という使い分けをすることで、安定性と機動性のバランスが取れた運用が可能になります。
次のパートでは、「じゃあ結局どっちを選ぶべきなの?」という疑問に対し、タイプ別のおすすめ早見表でわかりやすく整理します。
結局どっちがいい?|タイプ別おすすめ早見表
ここまでETFと投資信託の特徴や違いを詳しく解説してきましたが、
最後に「自分にはどちらが向いているのか?」を判断するためのタイプ別の早見表をご紹介します。
| こんな人におすすめ | おすすめ商品 | 理由 |
|---|---|---|
| 投資が初めて/よくわからない | 投資信託 | 自動積立・再投資が可能。操作が簡単で放置OK |
| 毎月コツコツ積み立てたい | 投資信託(つみたてNISA対応) | クレカ積立やポイント投資が可能 |
| コストを最重視したい | ETF | 信託報酬が非常に低く、長期運用に有利 |
| 取引タイミングを自分で決めたい | ETF | リアルタイムで売買できるので裁量性が高い |
| 新NISAの枠をフル活用したい | 投資信託+ETFの併用 | つみたて投資枠×投資信託+成長投資枠×ETFの組み合わせが◎ |
どちらが正解というより、「自分のスタイルに合った商品を選ぶこと」が成功の鍵です。
迷ったらまずは投資信託で少額から始めて、慣れてきたらETFにもチャレンジしてみる――そんな段階的なステップもおすすめです。
次のパートでは、この記事の総まとめとして、今後の行動のヒントをお届けします。
まとめ|迷ったら“自分に合ったスタイル”で選ぼう
ETFと投資信託は、どちらも分散投資ができる優れた金融商品です。
しかし、購入方法・コスト・運用スタイルには違いがあり、どちらが良いかは「あなたの投資スタイル」によって異なります。
今回の記事では以下のようなポイントを解説しましたーー
- 投資信託は自動積立ができ、初心者にやさしい
- ETFはコストが低く、リアルタイムで取引可能
- 新NISAでは、つみたて投資枠=投資信託/成長投資枠=ETFが基本
- どちらか一方でなく、併用も十分アリ
正解はひとつではありません。
自分のライフスタイルや投資経験、目標にあわせて、無理なく続けられる方を選ぶことが最も大切です。
まずは少額からスタートして、「実際に運用しながら学ぶ」ことが、資産形成への第一歩です。
▶ 楽天証券で新NISAをはじめてみる(無料口座開設はこちら)
